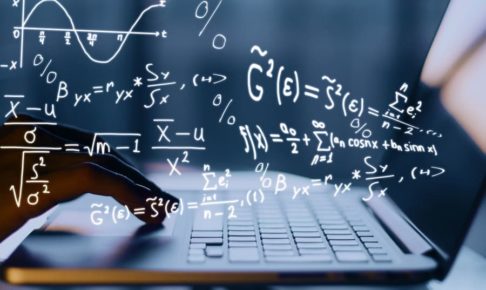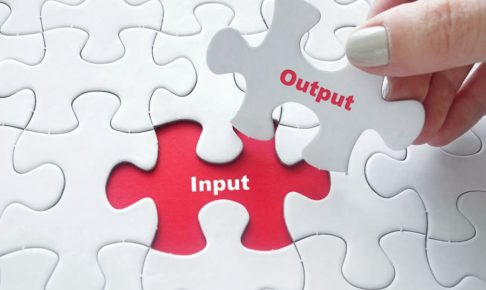あなたは社会人になってからどれくらい勉強をしていますか?
「社会人になってから勉強する時間が減った(なくなった)」という方が多いと思います。
勉強しないといけないという意識はあっても、実行に移すのはなかなか難しいですよね。
そこで今回は、社会人の勉強に関する実態から社会人こそ勉強するべき理由、勉強を続けるコツまで徹底解説します!
目次
社会人は平均1日6分しか勉強していない

勉強をたくさんしてきた学生生活に比べて、ほとんど勉強することがなくなる社会人。
普段は業務に追われて、休日は自由な時間として使い…勉強する暇なんてない!という方が多いですよね。
平成28年に総務省が行った調査では、日本の社会人はなんと平均で1日6分しか勉強をしていないという結果が出ています。
情報参照元:平成28年社会生活基本調査
小中高生は1日平均80分(授業は除く)という結果に対して社会人はなんと一桁。
また海外では、学生や社会人関係なく数時間は勉強をしている人がほとんどだそうです。
ここまで日本の社会人の勉強時間が短いとなると少し焦ってきますよね…
いくら忙しいとはいえ、通勤時間などもう少し時間はあるはず…
なぜ社会人になると勉強の時間がここまで減ってしまうのでしょうか?
なぜ社会人は勉強ができないのか?
忙しくて時間がない
多くの人が勉強をできない理由は、時間がないことでしょう。
普段は朝から夜まで業務を行い、残業で遅くまで残ることも。
通勤時間にやろうと思っても、疲れて移動中は寝てしまう…
家に帰るころにはヘトヘトで次の日のために早く寝ないと…
やっとの思いで帰宅してからさらに勉強なんて
頭がおかしくなるよ!
もうこれ以上情報は頭の中に入らないよ!
なんて思ってしまいますよね…
何を勉強したら良いか分からない
「勉強しなきゃとは思うけど実際何を勉強したらいいのか分からない」
という人も多いと思います。
業務に関することはもちろん、できれば資格も欲しい…なんて考えて結局勉強を始めずに終わってしまうケースもあります。
そもそも勉強の必要性を感じない
そもそも勉強の必要性を感じなければ、ほとんどの人が勉強はしないでしょう。
学生時代は勉強をしなければテストの点が伸びず成績が悪くなり…と目に見えて自分に影響が出るので「勉強しなきゃ」となりますが、社会人の勉強は強制ではありません。
勉強しないからといって、特別成果が出なくなるわけでもなければクビになることもありません。
勉強しなくても業務に影響なく何とかやっていける、という状態で勉強に必要性を感じない人も多くいます。
社会人こそ勉強するべき3つの理由

忙しい社会人でも「勉強が必要」と言われる理由はあるのでしょうか?
社会人にも勉強が必要な理由を解説していきます。
できる仕事が増える
自分の担当業務に関する勉強をすれば、できる仕事が増えるのは想像できますよね。
業務中に分からないことが出てきてその都度調べていては、できるようになることもあまり増えないでしょう。
日ごろから勉強をしていれば調べる時間と手間は少なくなり、その分業務スピードも速くなります。
人脈の構築につながる
勉強として外部のセミナーに参加すれば、通常の業務では築けない人脈が構築できます。
同じ業界の人と繋がることができれば、仕事を頼めたり依頼されたりという関係に発展することも考えられます。
給料アップに繋がる
できることが増えたり業務スピードが早くなれば、おのずと仕事上の結果もついてくるでしょう。
また自分にしかできない仕事が増えることで、自分の市場価値を高めることができますし、重要性が増せば会社にとって必要不可欠な人材になれます。
会社側は必要不可欠な人材は手放したくないので、高額な給料を払う価値があるとみなし、給料アップに繋がるでしょう。
先述したように、社会人の勉強は義務ではありません。
しかし、勉強しなかった人は知識やスキルが身につかず、キャリアアップも難しいでしょう。できることの幅も広がりません。
勉強はした分だけ自分のスキルとなりプラスになります。
スキルは身につけたらなくなることはなく、一生自分のものになりますよね。
また、会社によっては勉強の支援をしてくれる制度があります。
書籍の購入代やセミナーの参加費など、勉強に関することの支援があれば勉強もしやすくなりますよね。
また、国の制度で教育訓練給付金という制度もあるのをご存知でしょうか?
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
また、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
書籍の購入代やセミナーの参加費など、勉強に関することの支援があれば勉強もしやすくなりますよね。
ぜひ一度、国や自社の制度を確認してみてください。
社会人が勉強するべきこととは?

担当業務に関すること
やはり業務に関する勉強は重要です。
日々の業務の中でも勉強はできますが、スキルアップを目指すためには勉強で知識をつけるのが良いでしょう。
また、業務中に分からなかったことを復習として勉強したり、これから行う業務の予習といして勉強したり…
知識が増えることで業務スピードも上がってきます。
業務スピードが上がれば残業時間が減ったり、業務の前倒し対応ができ時間や心にも余裕ができる、などのメリットが考えられます。
今の仕事で活用できる資格・分野
社会人は資格の勉強もおすすめです。会社によっては特定の資格に「資格手当」を設定している場合もあります。
資格を持っておくことでスキルとして履歴書などにも記載することができ、知識を持っている証明にもなります。
資格といっても、「事務系の仕事だから簿記の資格」「秘書系の仕事だから秘書検定」と業務に直結するようなもの以外でも構いません。
例えば、最近では「コミュニケーション能力認定資格」というものもあります。
また最近のテクノロジーの発達に伴って重要性が認識されているのが、数学です。ビジネスにおいて統計や確率の考えを用いることも増え、社会人向けの数学教育サービスが人気になっています。
困ったら英語を学ぶ

やっぱりどのような仕事をするにしても「勉強したほうがいい」といわれるのが英語ですよね。
英語ができれば、取引先の担当者が日本人でなくてもでもスマートに対応できたり、海外で仕事をすることが可能になったりと人生における選択肢の幅が広がります。
分かりやすい英語学習の目的を持ちたいのであれば、TOEICがおすすめです。
試験日が決まっていて、点数として結果が見えるので目標設定がしやすいでしょう。
TOEICで高得点を獲得しておくと、転職の際など「ある程度英語ができる人材」だと判断してもらえます。
また、英会話スクールに通いスピーキングを学べば英語でのコミュニケーションをとることができ、さらに仕事の幅も広がります。
勉強はインプットとアウトプットの繰り返し
学生時代の勉強はテストでいい点を取るための勉強、課題を提出するための勉強が多かったのではないでしょうか。そのため一度勉強しても数日後には忘れている…なんて経験はないでしょうか?
ですが社会人の勉強は違います。
勉強でインプットを行ったら、実際に実行してアウトプットすることが重要です。
インプットとアウトプットを繰り返し、知識を定着させることでスキルが身につくのです。
ただインプットしただけで終わり、ではあまり意味がありせん。学んだことを実行して定着させてこそ、社会人の勉強には意味があります。
ぜひこのインプットとアウトプットの繰り返しを意識してください。
忙しい社会人が勉強を続ける方法

習慣化する
継続するにはやはり習慣化することが大切です。
- 朝出勤前に30分勉強をする
- 通勤時間は勉強の時間にする
- 帰宅後、勉強してからお風呂に入る
など、どこのタイミングで勉強をするのか決めておくと習慣化しやすくなります。
行動心理学では、人が行動を習慣化するには「3ヶ月」かかると言われています。
まずはじめは3日やってみる。3日続けられたら2週間を目標に続ける。2週間の目標が達成できたら1か月3ヶ月を目指して続ける。
など短期間の目標設定から始めるのが効果的です。
小さなことからはじめる
なかなか習慣化できない…という方は小さなことから始めてみましょう。
いきなり「よし!明日から毎日3時間勉強をするぞ!」と決めても、きちんと実行できないこともありますよね。初日はよくても気づいたら三日坊主で終わっていたり…
そんな方は「まずは1日15分」「通勤電車にのったらまずは参考書を開く」など簡単にできる小さなことから始めていくのがおすすめです。
その小さなことが習慣化してきたら「1日30分」など行動のレベルを少しずつ上げていきましょう。
急に「毎日〇時間は勉強するぞ!」をハードルの高い目標を立てても、実際に行動し続けられる人はすくないでしょう。
まずは習慣化することを目標に小さなことから始めてみてください。
社会人におすすめの勉強場所
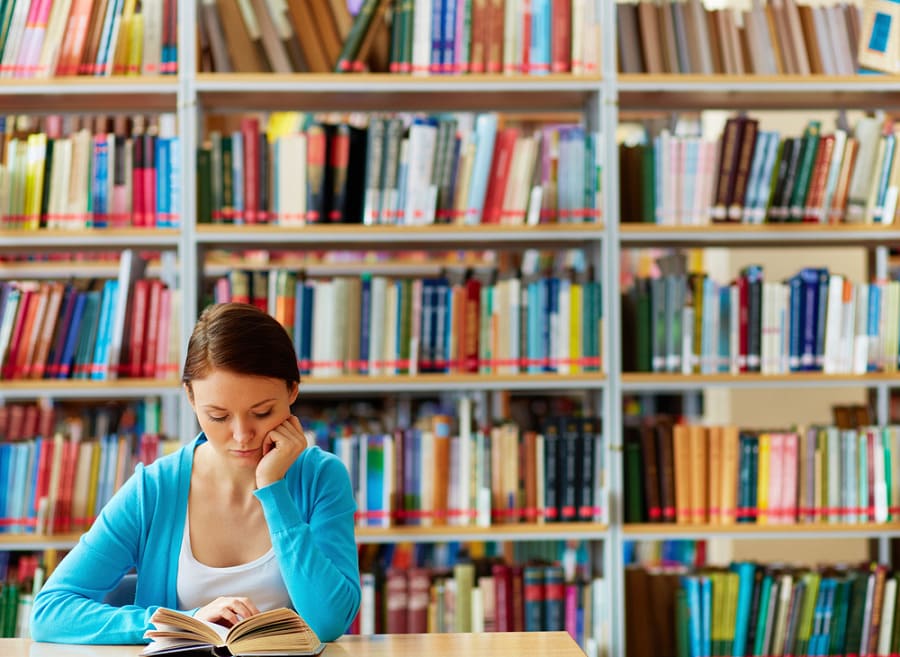
王道はカフェ
勉強場所の王道と言えばカフェですよね。
人の話し声や店内の心地良いBGMなどの音は、無音の空間よりも集中できると言われています。
また、コーヒーや紅茶に入っているカフェインは眠気覚ましにも有効的と言われているので、勉強するにはぴったりです。
最近ではコンセント完備のカフェも多いので、PCを使っての勉強もできます。お気に入りのカフェを見つけて勉強に励むのもいいかもしれません。
快適で集中できる図書館
誰にも邪魔されずに集中したい!という方にぴったりなのが図書館です。
読書や勉強目的で利用されるので、自分のモチベーション維持にも繋がりますし、館内は静かでとても集中できます。
夏は涼しく冬は暖かい、空調設備もしっかりしているので、快適に勉強ができるでしょう。
また、基本的に無料で誰でも利用することができるのも、図書館を利用するメリットの一つです。
自分のペースで頑張りたい人は自宅
人目を気にせず自分のペースで集中して勉強がしたい!という人は、やっぱり自宅での勉強がおすすめです。
「参考書持ってくるの忘れた!」などの忘れ物もなく、必要なものはすぐに使うことができます。
ただ、食べ物や趣味などのさまざまな誘惑が襲ってくるので「誘惑には負けない!」という強い意思をもって自宅での勉強に取り組むのがおすすめです…。
勉強している人が少ない今がチャンス

日本でも社会人になってから大学や大学院に入り直し、専門分野の勉強とキャリアを両立させる人が増えています。
しかし、欧米に比べればその数はまだ少なく、新卒でサラリーマンになった場合、大学までに身につけた知識と仕事を通して身につけた知識だけで、残りの人生を生きていく人も少なくありません。
現代は世界的に、先行きが不透明で予測のつかない時代となっています。このような生き方はいざという時に変化に対応できず、リスクの高い生き方になってしまいます。
これらの時代を生き抜くためには、日頃から自分自身の専門領域での知識を増やすだけでなく、英語やその他の外国語、数学などの基礎的な知識やプログラミングなどの最先端の情報に興味を持って勉強しておくことが必要です。
また、日本人は勉強をしている人が少ないと言いましたが、逆に言うと少し勉強をするだけで、周囲に差をつけられるということです!
業務に関することでもそれ以外のことでも、少しずつ学んでいけば必ず自分のスキルになるはず。勉強で周りの人よりも一歩リードしてチャンスをつかんでいきましょう。
勉強を続けるメリットは今後も大きくなっていく
社会人になっても勉強を続けている人は少ないですが、変化の大きい時代を生き抜くためには社会人こそ勉強が必要です。
ただ社会人は仕事や家庭生活で時間がなく、気合を入れて始めてしまうと三日坊主になりがちなのも事実です。継続するためにも生活を大きく変えず、小さなことから始めるのがおすすめです。
勉強=机の上にテキストなどを開いてガリガリというイメージもありますが、最近はYouTubeなどに勉強になる動画もたくさんアップされています。
またインターネット環境も整ってきているので、自分の好きな場所でのんびりと学ぶこともでます。
まずは1日に1回本を開く・通勤時間にYouTubeで英語のリスニングをするなど、気軽にできるところから始めましょう。